SESの面接でよく聞かれることは?好印象を与えるコツや逆質問例を解説

SESを経由して案件を希望する場合、プロジェクトの参画前に常駐先と面接が実施されます。SES企業の採用時に行われる面談をこなすだけではエンジニアとして就業することは認められません。
SES面接でスムーズに案件が決まる方もいれば、思うように決まらない方も少なくありません。そのため、徹底的に準備して入念な対策を施したうえで本番に臨みましょう。
今回はSES面接の役割や流れ、よく聞かれることや好印象を与えるコツを紹介します。
目次
SESの面接の役割と流れ

SESの面接とはプロジェクトの参画前に常駐するクライアント、担当営業とエンジニアとの間で行われる顔合わせです。当日はエンジニアの自己紹介、業務内容の説明、不明点や疑問点の確認を実施します。
面接の目的はスキル確認・適性判断、コミュニケーション力の評価です。面接をせずいきなり常駐するクライアント先にエンジニアを派遣した場合、スキル不足や相性が原因でミスマッチが起こり貢献できない可能性があります。
エンジニアが希望の案件と適切な職場環境の下、存分に力を発揮するためにも常駐するクライアントとの面接は重要な意味を持ちます。一般的なSES面接の流れは次のとおりです。
- 案件説明
- 双方の自己紹介
- スキルセットの確認
- 逆質問
- クロージング(合否連絡)
SESの面接だからといって特別な行程は特になく、基本的な流れは就職や転職の面接と変わりません。合否連絡は面接後1〜2日のうちに行われるケースが一般的です。
SESの面接でよく聞かれること

通常の面接と同様、回答のクオリティがSES面接の合否を分けるポイントです。事前に質問の内容を想定し、しっかり準備することでオファー率を高められます。
SESの面接でよく聞かれる質問は次のような内容です。
- 現在、勉強していること
- エンジニアを目指した理由
- これまでの経験・スキル
- リーダー・マネジメント経験の有無
- 残業が可能かどうか
- 通勤時間
ここでは、SESの面接でよく聞かれる質問の裏にある背景・意図を解説します。
現在勉強していること
エンジニアとしての就業経験がない、もしくは経験の浅いエンジニアの場合、現在勉強していることを聞かれるでしょう。知識の量や深さを見極めて、現場で活躍できる力量があるかを図るための問いかけです。
勉強の方法(スクールor独学など)、言語やフレームワークの種類など具体的な回答を意識しましょう。面接官から深掘りされる可能性があるため、できる限り詳細まで伝えられるよう事前の準備が必須です。
エンジニアを目指した理由
未経験者や経験が浅い方のSESの面接では、エンジニアを目指した理由を聞かれる場合があります。この質問の意図は、責任感を持って業務を遂行できるかどうかを確認するためです。
そのため、エンジニアとしての将来的な目標や在り方、学生時代にプログラミングに興味を持ったきっかけなどを具体的に伝えることがポイントです。
明確な動機を伝えることで、辛いことに直面したときや仕事がうまくいかないときに業務を投げ出すことなく、業務を最後まで全うしてくれる人物であるという印象を与えやすくなります。
これまでの経験・スキル
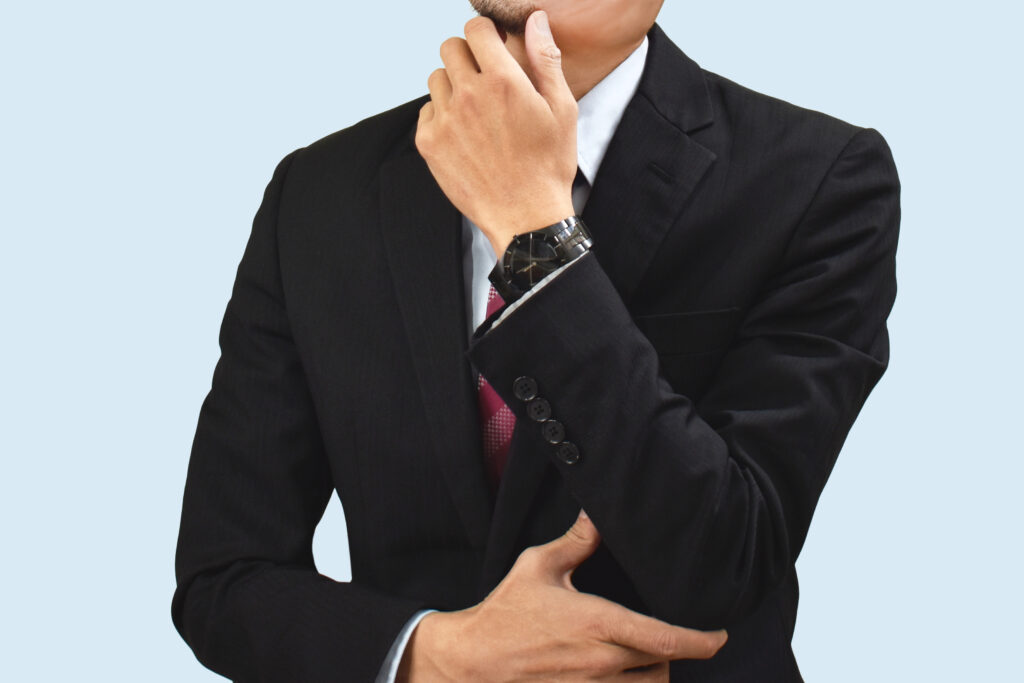
エンジニア経験がある場合、今までの開発経験やスキルの程度を細かく確認される可能性が高いでしょう。携わった案件やプロジェクトの規模、担当範囲をはじめ、具体的な回答を準備して面接に臨みましょう。
常駐先の面接官は、求めるスキルを備えたエンジニアかどうか見極めています。求める人物像や採用コンセプトを意識した回答が望まれやすいです。自身のスキルや実績などを整理しておきましょう。
ただし、実務経験やスキルに関する質問に答える際は、面接官に評価してもらいたいあまり、実際に経験したことや持っているスキル以上のことを伝えてはなりません。経歴を誇張すると面接に受かっても就業後、仕事についていけない可能性があるためです。
自身のスキルに合う企業で働くためにも、情報は誇張しないようにしましょう。
リーダー・マネジメント経験の有無
豊富な経験や高いスキルを持つ人材を求める案件の場合、プロジェクトのリーダーやマネジメント経験の有無を問われます。複数人のエンジニアを束ねて先陣を切って業務を進めた経緯がある場合、積極的にアピールした方がよいでしょう。
リーダーやマネジメント経験が必須のプロジェクトでない場合でも、依頼できる業務の幅が広がるため、質問するクライアントもいます。
これまでに経験があれば詳細をまとめ、最終的にどうなったのかも合わせて伝えるとより効果的でしょう。
私たちテクニケーションでは、スキルアップにつながるチーム制で案件を進めています。経験が浅い分野へ挑戦する際も、経験豊富なリーダーのサポートを受けながら案件にチャレンジすることが可能です。
また、自分が目指したい将来像に合わせてキャリアを構築できるように、案件を選択できる案件選択制を導入しています。さらに、テクニケーションでは各案件のリーダーを目指すことが可能です。
スキルや案件の裁量権を得たい方は、ぜひテクニケーションのカジュアル面談で、お気軽にご相談ください。
残業が可能かどうか

残業が可能か否かはSES面接の基本的な質問事項の一つです。契約時に明確な労働時間を伝えられる準委任契約や派遣の労働形態では原則、多大な時間外労働や休日出勤は発生しません。
しかしプロジェクトの進捗の遅れ、エンジニアの離脱、その他想定外の事情の発生などやむを得ない状況が生じる可能性も少なくありません。クライアント側は突発的な業務量の増大が見込まれるとき、当初の想定を超えても業務を依頼してもよいか見極めるために残業の可否を確認します。
このような場合、対応可能であることを伝えることで、選考を有利に進められる可能性があります。
通勤時間
SESの面接のなかには、勤務先への通勤時間に対する質問を受ける場合があります。通勤時間が長い場合、オフィスに出社する時間的なハードルが高くなりやすくなります。災害や交通機関の遅延などの影響を受けて、出社時間に間に合わない場面が想定されるでしょう。
また拘束時間の長時間化によるパフォーマンスの低下を招き、本来のスキルを発揮できなくなる事態も否定できません。
どうしても挑戦したい案件であれば、通勤時間を気にしないことを伝えたり、オフィスの近辺に引っ越すことを伝えたりするのも一つです。
SESの面接で好印象を与えるコツ

SESの面接で好印象を与えてプロジェクトにアサインされる確率を上げるには、以下のポイントを押さえましょう。
- 最初の自己紹介を徹底する
- 自分の強みと弱みを把握する
- 簡潔に話す意識を持つ
- 逆質問は複数準備しておく
それぞれ具体的に解説します。
最初の自己紹介を徹底する
最初の自己紹介では、自身の第一印象が決まります。そのため、自身の経歴や業務経験を端的に伝えることが重要です。ダラダラと話し続けず、要点を踏まえて短い時間で終わらせる意識を持ちましょう。
面接官によい印象を残すためには、話す内容のほかに振る舞いや声量、声のトーンも大切です。メラビアンの法則では、人同士の印象は言語以外の要素も重要であるといわれています。面接では聞き取りやすい声量やトーン、きびきびとした気持ちのよい動作を心がけましょう。
自分の強みと弱みを把握しておく
SESに限らず面接では自身の強みと弱みの両面を把握して、本番で淀みなく伝えることが重要です。自身の強みにつながる具体的なエピソードを用意しておくとよいでしょう。ただし長所や能力の高さなどポジティブな側面ばかり伝えると、面接官から「自信過剰で自分を客観的にとらえられていない」と判断される可能性があります。過剰なアピールはかえって、逆効果になる場合もあります。
弱みに関しては、聞かれたら答える程度で問題ありません。答え方としては、ネガティブな印象を残さないためにも、前向きな回答になるようにしましょう。克服を目指して行っている日々の努力や、改善を感じた出来事なども合わせて伝えましょう。
簡潔に話すことを意識する
面接時、質問に対して簡潔に話すことが求められます。長すぎる回答では、面接官に言いたいことが伝わりにくくなります。簡潔なコミュニケーションを実現するためにも、伝えたいこと、つまり結論を最初に述べることが大切です。
何よりもまず聞かれたことに明確に答える意識を持ちましょう。例えば「あなたの長所は何ですか?」と問われたら、「わたしの長所は〜です。」と冒頭に言います。強みと感じる理由や具体的な主張を補足する内容は後から伝えれば問題ありません。
エピソードトークの際にも要点を絞って、長すぎず端的に答える意識が必要です。
企業への逆質問は複数準備しておく
クライアントとエンジニアの間でミスマッチが起こらないよう、逆質問を設ける場合があります。逆質問の内容によっては評価される可能性もあるため、複数準備しておきましょう。逆質問の内容に関しては、次項にて例を挙げて説明します。
単に疑問点や不明点の解消を目的としたセクションではなく、業務に対する意欲や熱意を図る意図があります。逆質問がなければ、消極的な人材だととらえられ、マイナス評価につながる可能性が高いでしょう。
基本的に質問の数は多ければ多い程よいため、思いつく限り用意してください。貢献したいからこそ、プロジェクトの詳細をより詳しく知りたいという想いを持ちながら、質問を考えてみましょう。
SESの面接の逆質問例

ここでは、面接官に好印象を与えやすい逆質問例を紹介します。どのような逆質問をしたらよいのか迷っている方はぜひ参考にしてみてください。
- プロジェクトに参画できた場合、最初に担当する業務について教えてください。
- 私が今勉強中の〇〇は当案件と親和性が高いと考えています。ほかに活躍するために学ぶべきジャンルや言語、フレームワークがあれば教えてください。
- オファーに先立ち、案件に必要な資料を拝見することはできますか?
逆質問をすることで、疑問や不安を解消するだけでなく、自身のアピールチャンスでもあるため、積極的に質問しましょう。
SESの面接に成功する人の特徴

SESの面接にオファーし、すぐ常駐先が決まる方には共通の特徴があります。総じて準備を徹底する意識が強く、想定質問を用意して案件の内容を深くリサーチしている点です。
「自分は面接に受かるだろうか?」と不安を感じる方向けに、SES面接に成功する人の特徴を解説します。
事前準備を徹底している
入念な事前準備をしたうえで面接に臨む方はスムーズにオファーされる傾向がみられます。履歴書と職務経歴書は明確かつシンプルに記載し、十分な想定質問や逆質問を用意することを欠かしません。
また事前に模擬面接を受けて、好印象を与える声のトーンやスピードを意識して話せる状態にしています。面接の練習は必須ではないですが、緊張しやすい方やコミュニケーションがあまり得意ではない方は実施しておくと安心感があるでしょう。
数をこなすうちに上達する可能性があるため、本番を想定して話すトレーニングを積むことは効果的です。
案件内容について調べている
参画する案件の内容に関して主体的かつ徹底的に情報を収集しましょう。
業務や求められるスキルを把握し、自身の経験や強みと関連性があると伝えることでオファーの確率が上がります。プロジェクトだけでなく常駐先の企業に対する情報収集も重要です。オフィスの所在地や事業内容、商品・サービスなどはインターネットから手軽に調べられます。
勤務先に対するより詳細な情報が知りたいときは、担当営業に質問すると効果的です。自分ではリサーチできなかった求める人物像や採用コンセプトを入手することで、面接対策の精度を向上できるためです。
学習意欲の高さをアピールする
案件に必要な言語やフレームワークに対する学習意欲の高さをアピールしましょう。常駐するクライアントが得意領域に据える分野の習得に対する熱意を伝える方法でも問題ありません。特にスキルや開発経験のアピールが難しい未経験者の面接においては、学習意欲のアピールは重要です。
またプログラミングに限らず、勉強自体が習慣付いていると伝える戦略も有効です。学ぶ意識の高低は同程度のスキルや経験を持ち、どちらを採用するか迷うようなシチュエーションで最終的な判断の根拠となる可能性があります。
SESの面接に落ちる人の特徴

SESの面接に落ち続ける場合、自らの課題に気付いて改善する意識が求められます。面接に通過できず配属先がなかなか決まらない方の典型的なパターンは次のとおりです。
- 回答が具体性に欠ける
- 準備不足で答えが曖昧
- 学習意欲や前向きな姿勢が伝わらない
- 身だしなみに清潔感がない
- 質問に対する回答がずれている
- スキル不足
回答やコミュニケーションと同じくらい重要な要素は身だしなみです。豊富な経験や高いポテンシャルを示せたとしても、清潔感がなく、一緒に働くメンバーを不快にさせるリスクがある方はなかなかオファーに結びつきません。
プロジェクト単位で参画する案件でもチームの協力は不可欠です。技術力だけでなく、円滑なコミュニケーションが得意だと示すことが大切です。
テクニケーションでは、スキルアップにつながるチーム制にて案件を進めています。経験豊富なリーダーのもとで一緒に業務ができるため、自身の市場価値を高めるサポートが可能です。
また、JavaSilverやLPICなど会社が推奨する資格受験費用や、参考書代を支給する資格取得支援制度も導入しています。エンジニア一人ひとりのスキルアップができる環境が整っています。
さらにテクニケーションでは、案件選択制を採用しているため、自分が取り組みたい分野に合わせて案件を選ぶことも可能です。
理想のキャリアを目指すためにも、テクニケーションのカジュアル面談でぜひご相談ください。
SESで理想のキャリアを実現するために

SESの面接に通過してエンジニアのキャリアをスタートさせるためには事前の準備が重要です。書類対策や模擬面接、想定問答集など入念に対策をして臨めば、コミュニケーション力に自信がない方でも希望の案件に配属される可能性は十分あります。
しかし、目指すべきは自身の市場価値が高められる場を見つけることです。
テクニケーションは高還元SESを掲げ、エンジニアが働きやすい環境作りに注力しています。高還元SESとは、エンジニアへの報酬還元率が高いSES企業のことです。
テクニケーションでは、単価給与連動制を採用しています。案件の単価に応じて収入が決まるため、実力がある人ほど高収入を得やすい仕組みとなっています。そのため、成長したい分野や得意分野に専念しやすいでしょう。
また、テクニケーションでは、エンジニア自身が自由に案件を選べる案件選択制も導入しています。自身に合ったスキルや経験に基づいて、挑戦したい案件にチャレンジすることも可能です。さらなるスキルアップとキャリアの幅を広げ、市場価値を高められる環境が整っています。
希望のキャリアを実現できる環境がテクニケーションでは整っています。理想の働き方を私たちと一緒に叶えませんか?気になる方は、ぜひテクニケーションのカジュアル面談にてご相談ください。

















