SESと派遣のメリットとデメリット|それぞれの違いについても解説

エンジニアとしてのキャリアを考えるなかで、SESと派遣、どちらの働き方を選ぶべきか迷っていませんか?それぞれの特徴や違いがよくわからず、判断に困っている方も少なくないのではないでしょうか。
この記事では、SESと派遣、それぞれの契約形態の違いと特徴やメリットデメリット、働き方の判断基準などを詳しく解説します。
正しい知識を身に付けることで、あなたの希望するキャリアや働き方に合った選択ができるよう、ぜひ参考にしてみてください。
目次
SESのメリット

技術力の向上から人脈形成、安定した収入まで、総合的なメリットを得られるSESは、エンジニアのキャリア形成を支援するさまざまな利点があります。主なメリットは次のとおりです。
- 多様な環境でスキルを磨ける
- 人脈を広げやすい
- 収入が安定している
特に近年は、IT人材の需要増加に伴い、エンジニアの市場価値が高まっているため、自分のペースでスキルアップできるSESという働き方が注目を集めています。以下で詳しく解説します。
多様な環境でスキルを磨ける
SESの大きな特徴は、さまざまなクライアント企業で実務経験を積めるということです。一つの案件が終わると次の企業へ移動するため、異なる業界や環境で働く機会が広がるでしょう。
例えば、金融系システムの開発から製造業の基幹システム構築まで、幅広い分野のプロジェクトに携わることができます。それぞれの現場で求められる知識やスキルは異なるため、自然と技術力が向上していきます。多様なプロジェクトを経験することで、エンジニアとしての市場価値を高める機会となるでしょう。
人脈を広げやすい
SESエンジニアは、クライアントをはじめとする他企業の人々との協力関係を築くことができます。プロジェクトを遂行するため、さまざまな企業に所属する人々と協力して業務を進めることで、ビジネスのコネクションや人脈が自然と広がっていくでしょう。
さまざまな企業や業界の専門家との関係を築くことで、将来の仕事の機会やキャリアの発展につながる可能性が広がります。こうした人脈形成は、長期的なキャリア形成において大きな強みとなるでしょう。
収入が安定している
SESは、正社員として雇用されるため、安定した収入を得られます。SES企業の正社員という立場で働くため、派遣と比べて雇用の安定性が期待できます。
エンジニアの経験やスキルに応じて、年収3,500,000〜7,500,000円程度の幅で報酬が設定されるのが一般的です。また、業績や成果に応じて報酬が上がる制度を導入している企業も多く、市場価値に見合った収入を得られる環境が整っています。
SESのデメリット

SESには魅力的な特徴がある一方で、働き方の特性による課題もあります。ここでは、SESで働く際に知っておくべき注意点について解説します。
これらの課題を事前に理解し、適切に対応することで、より充実したSESエンジニアとしてのキャリアを築くことが可能でしょう。デメリットを把握することは、よりよい職場選びにもつながります。
環境が変わりやすい
SESの特徴として、クライアント企業が頻繁に変わる可能性があるという点が挙げられます。プロジェクトの終了とともに新しい職場環境に移ることになるため、適応力が求められます。
例えば、以下のような点に適応する必要があります。
- 新しい職場での人間関係の構築
- 異なる企業文化への順応
- 通勤経路や勤務時間の変更
このような環境の変化は、適応力の高い方にとっては働く魅力となりますが、変化が苦手な方にとってはストレスになりがちです。また、頻繁な環境の変化により、自分の所属する企業への帰属意識を持ちにくいという面もあります。
重要な部分は任されにくい
SESエンジニアは、クライアント企業の正社員と比べると、重要な意思決定や中核的な業務に関与する機会が限られる場合があります。
重要な部分が任されにくいのは、SESエンジニアがクライアント企業の社員ではなく、外部の人間であると扱われるためです。一般的に、上流工程はクライアント企業の正社員が担当し、SESエンジニアは実装フェーズを担う傾向があります。
しかし、個々のスキルアップやキャリア向上を目指せる体制が整っているSES企業であれば、意思決定や中核的な重要な部分に関与できる機会は十分あります。
私たちテクニケーションでは、案件選択制やチーム制により、個々のスキルアップやキャリア向上を考慮した働き方を実現できます。チームのメンバーから各案件のリーダーを目指すこともできるため、意思決定や中核的な重要な部分に関与することも可能です。
ぜひテクニケーションで理想の成長環境を見つけてみませんか?まずはカジュアル面談で、理想とするキャリアについてお話をお聞かせください。
派遣のメリット

派遣での働き方には、キャリア形成とプライベートの両立を実現できるさまざまな利点があります。ここでは、派遣ならではのメリットについて詳しく解説します。
昨今のワークライフバランス重視の流れを受けて、自分のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を選べる派遣という選択肢が、より一層注目を集めているでしょう。
多様な環境でスキルを磨ける
派遣として働くことにより、さまざまな企業やプロジェクトで経験を積むことができます。
具体的には以下のようなスキルアップが期待できます。
- さまざまな業界のシステム開発に携われる
- 異なる開発手法や技術に触れられる
- 短期間で幅広い実務経験を積める
派遣先企業の求めるスキルと自身の能力が一致すれば、新しい案件に参加しやすく、短期間で多様な業務経験を積むことができるでしょう。
ワークライフバランスが取りやすい
派遣の大きな特徴として、契約期間や勤務時間が明確に定められている点が挙げられます。残業や休日出勤が少ない職場を選べば、自分の時間を確保しやすくなります。
また、労働条件についても要望を伝えやすい環境があり、勤務時間の調整が可能です。プロジェクトの期間もあらかじめ決められているため、次のプロジェクトまでの期間を自分でコントロールすることもできます。このような柔軟性により、仕事と私生活のバランスを整えやすくなっています。
派遣先からのオファーが期待できる
派遣社員として働くなかで、優れた結果を残すことができれば、派遣先企業から直接雇用のオファーを受ける可能性があります。派遣期間を通じて自分の能力や人柄を理解してもらえるため、正社員としてのオファーにつながることも少なくありません。
厚生労働省の定める派遣法でも、派遣期間終了後の直接雇用は認められており、キャリアアップの選択肢の一つとして考えることができます。実際の業務を通じて企業の文化や風土を理解したうえで、正社員としてのキャリアを選択できる点も魅力です。
派遣のデメリット
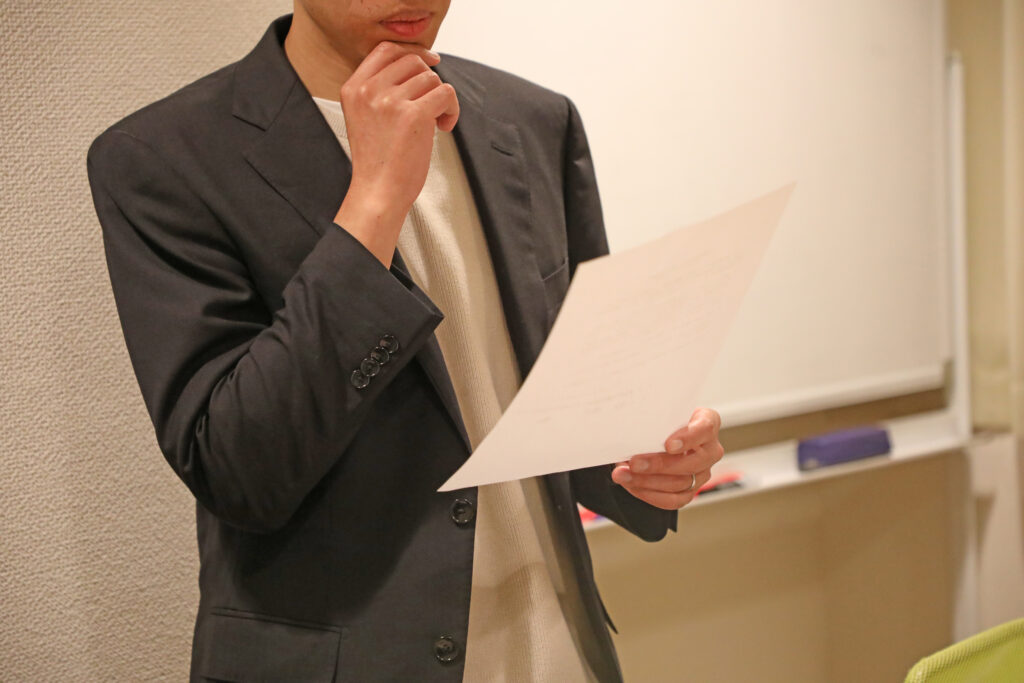
派遣での働き方には、雇用の安定性とキャリア形成に関する課題があります。これらのデメリットを理解したうえで、自分に合った働き方を選択することが重要です。
身分が不安定
派遣社員の大きな課題は、雇用の継続性が保証されていない点です。労働者派遣法により、一つの職場で働ける期間は最長3年と定められています。契約期間が終了した後、次の仕事が見つかるまでは派遣待ちの状態となり、収入が途絶えるリスクがあるでしょう。
また、景気が悪くなったり企業の考えが変わったりすることで、契約期間の途中で仕事がなくなってしまうこともあります。SESと違って、派遣会社との結びつきが緩やかなため、継続的に収入を得られるかどうか不安定な面があります。
キャリアアップが難しい
派遣社員は、同一職場での長期的なキャリア形成が制限される傾向にあります。3年という期間制限があるため、一つの職場で専門性を深めたり、重要な責任を任されたりする機会が限られます。
同じ職場で長く働く正社員の方と比べると、仕事の経験を積みにくかったり、重要な仕事をまかせてもらえたりする機会が少なくなりがちです。しかし、派遣先の企業で頑張って実績を重ねることで、その会社の正社員として働くチャンスが生まれることもあります。一つひとつの経験を大切にすることで、新しいキャリアへの道が開ける可能性があります。
SESと派遣の違い

エンジニアとして働く際の契約形態には、SESと派遣という2つの選択肢があります。契約内容や指揮命令権の違いを理解することで、自分に合った働き方を選べます。
IT業界ではどちらの働き方も一般的ですが、その特徴をしっかり理解しておくことが大切です。
SESは指揮命令権がベンダー企業にある
SESの場合、エンジニアはSES企業(ベンダー企業)と準委任契約を結びます。これは、派遣とは異なる特別な契約形態です。エンジニアは、クライアント企業に常駐しますが、あくまでもSES企業の社員であり雇用関係もSES企業と結ばれています。
具体的な特徴は以下のとおりです。
- SES企業の正社員として働く
- 雇用関係はSES企業と結ばれる
- 業務指示はSES企業から受ける
クライアント企業が直接SESエンジニアに業務指示をすると、労働者派遣法で禁止されている偽装請負となるリスクがあります。そのため、業務の指示系統は必ずSES企業を通す必要があります。このように、SES契約は労働者派遣法の適用を受けない契約形態であることが特徴です。
派遣は指揮命令権がクライアント企業にある

派遣とSESの違いは、契約内容と指揮命令権にあります。派遣の場合は、派遣会社と契約を結び、派遣先企業に対して労働者を提供する仕組みです。
具体的な特徴は以下のとおりです。
- 派遣元企業と雇用契約を結ぶ
- 指揮命令は派遣先企業から受ける
- 契約形態は労働者派遣契約となる
派遣エンジニアと派遣先企業の間に直接の雇用関係はありませんが、業務の指示は派遣先企業から直接受けることになります。また、SES契約と同様に、労働力に対して報酬が発生する仕組みとなっています。
報酬が労働時間に対して発生する点は同じ
SESと派遣では契約形態は異なりますが、働いた時間に応じて報酬が発生するという基本的な仕組みは同じです。この点は、エンジニアの労働に対する適切な評価という観点で重要です。
ただし、報酬の支払い方には違いがあります。
- SES:SES企業から給与として支払われる
- 派遣:派遣会社から給与として支払われる
一般的なSES企業の報酬体系では、エンジニアの労働力に対して契約時に定められた報酬が発生します。スキルや経験に応じて適切な報酬を得られる仕組みが整っており、市場価値に見合った評価を受けることが可能です。
このように、SESと派遣ではそれぞれ特徴が異なります。よりよいキャリア形成を目指すなら、高還元SESという選択肢も検討してみましょう。
高還元SESとは、エンジニアの単価に対する還元率が高いSES企業を指します。私たちテクニケーションでは単価を開示することで、納得のうえキャリアを重ねることが可能です。
また、案件選択制を採用して希望に沿った案件マッチングを実現しています。チーム制による技術的なサポート体制も整っているため、安心感を持ってスキルアップに取り組めます。
自分の市場価値を高めながら、納得のいくキャリアを築きたい方は、まずはテクニケーションのカジュアル面談でお気軽にご相談ください。
将来性のあるSES企業を選ぶためのポイント

SES企業を選ぶ際は、エンジニアの成長をサポートできる環境が整っているかをしっかりと確認することが大切です。以下の4つのポイントに注目して、自分に合った企業を見つけましょう。
まず、企業の取引実績を確認しましょう。大手企業との取引がある企業は、技術力や信頼性に優れ、上流工程に携わるチャンスが広がるでしょう。
次に、研修や教育制度の充実度をチェックします。未経験からエンジニアを育てる体制が整っている企業は、長期的な人材育成に力を入れています。特に上流工程に携わるための研修制度がある企業は、エンジニアのキャリアアップを重視しているといえるでしょう。
3つ目は評価制度の透明性です。報酬や昇進の基準が明確で、キャリアパスが見えやすい企業を選びましょう。
最後に企業の収益性と待遇を確認します。利益を出している企業はエンジニアへの還元率が高く、充実した給与や福利厚生を提供できるでしょう。このような環境で長期的なキャリアを築けます。
メリットを活かせる高還元SES企業を選ぼう

ここまでSESと派遣それぞれの特徴について、以下の3つのポイントを解説しました。
- SESと派遣では契約形態と指揮命令系統が異なる
- 両者にはそれぞれ固有のメリット・デメリットがある
- 高還元SESなら安定性とキャリアアップを両立できる
高還元SESのなかでも、テクニケーションはエンジニアの成長を第一に考えた環境づくりに力を入れています。
テクニケーションでは、案件選択制とチーム制を組み合わせ、エンジニアの市場価値に見合った報酬と着実なスキルアップの機会を提供しています。そのため、成長したい分野や挑戦したい分野に専念することも可能です。
また、単価給与連動制により、スキルアップが収入アップに直結する仕組みも整っています。
年収アップやスキルアップを目指したいという方は、まずはテクニケーションのカジュアル面談で、お気軽にご相談ください。

















