SES契約と準委任契約は違うの?紛らわしい契約形態や注意点を解説

SEとして働く際、SES契約や準委任契約にて契約を結び業務を行いますが、契約内容や違いについて詳しく知らない方もいるかもしれません。
SES契約と準委任契約の違いは紛らわしく、混同されやすいです。本記事では、SES契約やほかの契約形態との違い・SES契約にて注意すべき点・SES契約のメリットやデメリットなども解説します。
SES契約について正しく理解し、自身にとってよいSES企業で働けるようにしましょう。
目次
SES契約と準委任契約の関係

ここでは、SES契約と準委任契約の関係を説明します。それぞれの契約形態の違いを理解することで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。また、自分に合う契約形態を選択するためにも、以下で詳しく解説します。
SES契約とは
SES(システムエンジニアリングサービス)契約ではベンダー企業がクライアント企業にシステムエンジニアを派遣し、システムエンジニアが働いた分の報酬をクライアント企業が支払います。ベンダー企業がクライアント企業に専門技術者を提供する契約ということです。
SES契約を結んだシステムエンジニアは、クライアント企業(派遣先企業)でシステム運用や保守、インフラ環境構築などを行います。
準委任契約とは
準委任契約とは法律行為以外の業務を依頼する契約のことで、一例を挙げるとプログラマーによるシステム開発などが該当します。SES契約は準委任契約ですが、厳密にいうと、SES契約と準委任契約には異なる部分があります。
SES契約ではシステムエンジニアがクライアント企業のプロジェクトに参画し、専門技術を提供します。そのうえで、行った業務時間に対して責任を有し、報酬が支払われる仕組みです。
一方、準委任契約でもエンジニアがクライアント企業で業務を行うのは同じです。ただし、2種類の契約タイプがあります。
- 履行割合型:労働時間に対して対価が支払われる契約
- 成果完成型:依頼されたものを納品すると対価が支払われる契約
このように、SES契約は履行割合型の準委任契約に分類されます。
SES契約以外の契約形態と違い

システムエンジニアの契約形態には、SES契約以外にもさまざまな種類があります。契約の種類は次のとおりです。
- 委任契約
- 請負契約
- 派遣契約
- 雇用契約
- 業務委託契約
それぞれの特徴を整理し、違いを明確に説明します。
委任契約
委任契約とは法律行為を依頼する際の契約形態です。法律行為はその行為を実行することで法的な効果を生じさせる行為を指します。
例えば消費者が商品を購入すると、売買契約が成立し、法律上の効果が発生します。そのため、これは委任契約となるのです。
システムエンジニアの業務遂行によっては法的効果は発生しません。そのため、SES関連では準委任契約の方が適用されます。
請負契約
請負契約は請負人であるシステムエンジニアが仕事を完成させ、成果物に対する対価を受け取る契約形態です。準委任契約では業務の遂行が報酬の対象になりますが、請負契約では完成した成果物の納品で報酬が支払われます。
もし成果物に問題や不具合があるときは、すみやかに修正対応しなければいけません。また、不具合の状態がひどければ、損害賠償請求されることもあります。
派遣契約

SES契約と派遣契約は似ているように見えますが、指揮命令権の所在が異なります。SES契約ではベンダー企業側に指揮命令権があるのに対して、派遣契約ではクライアント企業側にあります。
そのため、クライアント企業は派遣されてきたシステムエンジニアに対してフレキシブルに指示を出せるのです。
SES契約ではベンダー企業が指示を出すのでクライアント企業の希望とは異なる業務になってしまうことがあります。一方、派遣契約なら指示を出すのがクライアント企業になるので、期待どおりの業務をしてもらえるでしょう。
雇用契約
雇用契約は準委任契約や請負契約などのほかの契約形態とは異なり、システムエンジニアが雇用主の元で業務を行い、その対価として賃金を受け取る契約のことです。完全に雇用主の傘下に入るため、ベンダー企業との関わりはありません。
雇用契約では使用従属性という関係になります。雇用主とシステムエンジニアの間における主従関係のようなものです。これはほかの契約形態には見られない条件です。
業務委託契約
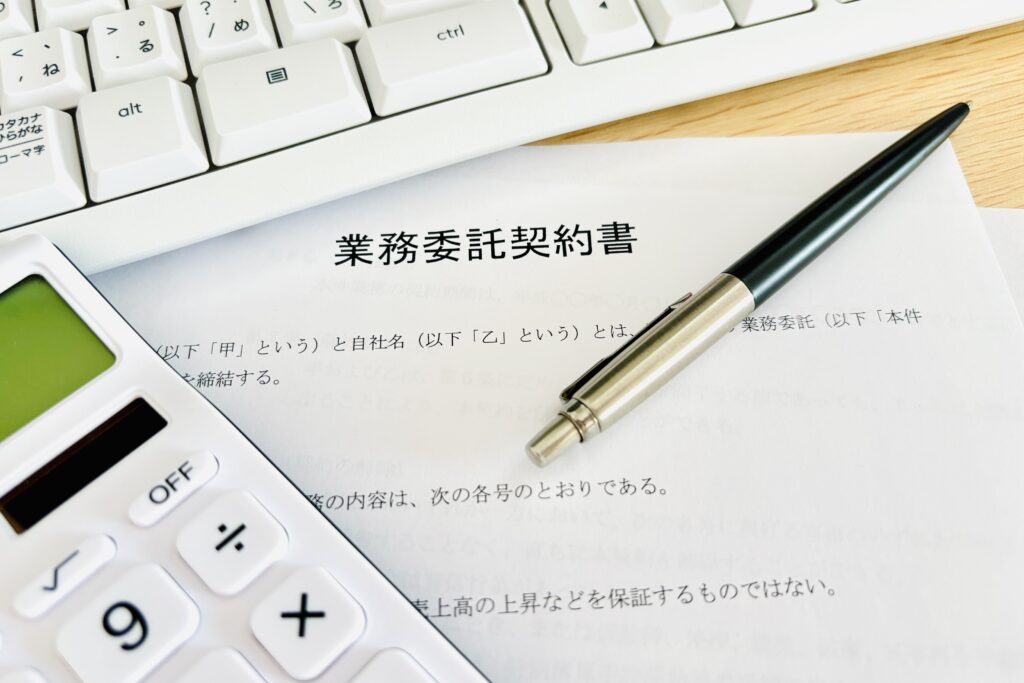
業務委託契約は自社の業務の一部もしくは全部を外部企業に委託する契約です。業務委託契約にはこれまで取り上げたSES契約・準委任契約・請負契約などすべてが含まれます。
業務委託契約では委託者から指示を受けることもなく、自由な働き方ができるのがメリットです。システムエンジニアとしての専門スキルを活かしながら、年収アップも期待できます。
SES契約で注意すべきこと

SES契約を行う際、次のような注意点があります。
- 指揮命令権の所在があいまいになっていないか確認する
- 実態が二重派遣になっていないか確認する
注意点を見逃しているがゆえにリスクを生じることもあるので、よく確認したうえで臨みましょう。
指揮命令権の所在があいまいになっていないか確認する
SES契約を結ぶ際に、必ずチェックしておくべきポイントは、指揮命令権の所在です。指揮命令権があいまいになっていることはないでしょうか。
本来は、SES契約における指揮命令権はベンダー企業にありますが、クライアント企業にはありません。クライアント企業がシステムエンジニアに対して指示を出すと、偽装請負となってしまうことがあります。
クライアント企業とシステムエンジニアの間には雇用関係はなく、業務遂行はエンジニア自身が行うことです。指揮できるのはベンダー企業のみとなります。このあたりをしっかり確認したうえで、SES契約を結びましょう。
実態が二重派遣になっていないか確認する
二重派遣とは、派遣元企業が派遣したシステムエンジニアを受け入れた企業がそのエンジニアをさらに別の企業に派遣する行為を指します。
具体的な例を挙げてみましょう。派遣元A社がシステムエンジニアを派遣先B社に送ったとします。本来はそのシステムエンジニアはB社で働くべきですが、B社がそのままエンジニアをC社に送り手数料を得る、これが二重派遣です。
二重派遣は違法行為です。理由は労働者の雇用責任があいまいになること、労働者の雇用条件が低くなることなどによります。
しかし、意外にもSES契約でも二重派遣が起きることがあります。このような状態になっていると、システムエンジニアにとっても不利なことが多々生じるので、契約内容をよく確認したうえでSES契約をするようにしましょう。
SES契約をするメリット

システムエンジニアがSES契約をするメリットは、次のとおりです。
- 経験値が増える
- 残業が少ない
- 長期契約なら安定した収入が得られる
SES契約をすることは、システムエンジニアにとって有益な面が多いのが特徴です。以下で詳しく解説しますので、参考にしてみてください。
経験値が増える
SES契約では、さまざまな企業での業務経験を積む機会が増えます。その結果、多様な技術や業務フローを学ぶことができ、スキルアップにつながります。
1つの企業に留まらず、多様なプロジェクトに携わることで、幅広い技術や業務知識を習得できるでしょう。そのため、キャリアの選択肢が増える可能性があります。
私たちテクニケーションでは、案件選択制の採用によってキャリアの幅を広げたいエンジニアのために、より多くの案件を選択できる環境を整えています。この制度を通じて、成長したい分野や挑戦したい分野に専念することが可能です。
また、チーム制も採用しているため、大きな案件やチャレンジしたい案件への挑戦もできることからスキルアップできる機会が豊富です。
「キャリアの幅を広げたい」「挑戦しやすい環境に身を置きたい」という方は、テクニケーションのカジュアル面談でぜひお話をお聞かせください。
残業が少ない
SES契約では、成果物ではなく、労働時間に対して報酬が支払われます。そのため、納期のプレッシャーが少なく、比較的残業が発生しにくい傾向にあります。
契約内容に基づいて一定時間働けば報酬が支払われるということであり、無理な働き方をする必要はないでしょう。
長期契約なら安定した収入が得られる
SES契約の場合、月給制や固定制を採用している企業が多い傾向にあります。たとえ、業務自体が完了しても安定した収入を得られます。これにより、長期的な計画も立てやすくなり、不安を抱くことなく仕事も生活もしやすくなるでしょう。
SES契約をするデメリット

SES契約には、以下のようなデメリットもあります。
- 指揮命令権があいまいになるリスク
- 案件の終了後に次の案件が見つかるまで不安がある
- 環境の変化が激しい
リスクや問題点を知らずにいると不安になることもあるでしょう。不安を解消するためにも、確認しておきましょう。
指揮命令権があいまいになるリスク
SES契約では指揮命令権の所在地はベンダー企業になります。ところが、クライアント企業のなかにはこの点を十分理解していないところがあり、勝手にシステムエンジニアに指示を出すこともあるのです。
そうなると、指揮命令権が混乱し、エンジニアも対応に苦慮する場面が出てくるでしょう。
しかしSES契約において、クライアント企業が直接エンジニアに指示を出すと、労働者派遣法違反となる可能性があります。クライアント企業から直接指示を受けた場合は、ベンダー企業に相談し、契約の範囲内で対応することが重要です。
案件の終了後に次の案件が見つかるまで不安がある
SES契約終了後、次の案件が決まるまでの期間を待機期間と呼びます。待機期間が長引くと、収入やキャリアの不安が生じることがあります。
待機期間中の給与ですが、社内待機なら100%支給され、自宅待機の場合は勤務扱いで100%、休業扱いで60%以上の支給です。
100%給与が支給される場合でも、仕事がない状態が続くと不安を感じることがあります。
待機期間中は、スキルアップの勉強や次のSES案件の準備を進めるとよいでしょう。場合によっては転職も選択肢の一つになります。
環境の変化が激しい

SES契約では、さまざまなクライアント企業で働くことになります。出向先が多くなるので、そのたびに大きく環境が変化します。
そのため、激しい環境の変化に順応するのがうまくない方の場合、苦労することになるでしょう。人間関係の変化に対応するのが得意でない方の場合、ストレスも溜まりやすくなります。
SES企業を選ぶときのポイント

SES契約をするためにはSES企業を探さなければいけませんが、どのような基準で選べばよいでしょうか。次のようなポイントをもとに、自身のキャリアにふさわしい企業を選びましょう。
- 取引先を確認する
- エンジニアの待遇を確認する
- 技術力を確認する
- 報酬システムが明確か確認する
- フォロー体制の充実度を確認する
それぞれのポイントを、以下で詳しく解説します。
取引先を確認する
SES企業を選ぶ際は、取引先を確認しましょう。取引先にSES企業が多いと、商流が深いことになります。商流が深いと多重構造になりやすく、単価が下がりやすいです。
逆に取引先にユーザー企業がかなりあるようなら、営業力が高い証拠で充実した仕事量、それも条件のよい仕事を確保できることになります。
そのため、ユーザー企業との直接取引が多いSES企業の方が、案件単価が高くなりやすい傾向にあります。
エンジニアの待遇を確認する
SES企業を選ぶ際には、給与や福利厚生の充実度も重要な要素です。待遇がよい企業では、エンジニアのモチベーションが向上し、仕事のパフォーマンスも上がりやすくなります。
よりよい環境で業務を遂行するためにも、どのような待遇があるのか確認しましょう。
技術力を確認する

SES企業の技術力も選ぶ際に見逃せないポイントです。企業のホームページなどから、SES企業がどのような技術力を持ち、どのような分野が得意かを確認しておきましょう。
企業に直接問い合わせて確認することもできます。その内容と自分のスキルが一致すれば、選択の候補として検討しましょう。
報酬システムが明確か確認する
SES企業の報酬体系がどうなっているかは選ぶうえでも重要なポイントです。報酬体系が明確なら、心配しないで働くことができます。
高還元SES企業なら、システムエンジニアへの還元率も高く設定され、報酬も高くなりやすいです。
フォロー体制の充実度を確認する
SES企業が、どのようなフォロー体制を取り入れているのか確認したうえで選びましょう。システムエンジニアやクライアント企業へのフォローが充実しているSES企業なら、問題が発生したときも適切にすばやく対処することができます。
また、心強いサポートがあれば実務経験を積めるため、自身のキャリアアップにもつながるでしょう。
テクニケーションでは、チーム制を採用しているため、経験が不安な分野の案件でも、ベテランエンジニアによるサポートを受けながらスキルチェンジをすることも可能です。
また、キャリアの幅を広げたいエンジニアのために、より多くの案件を選択できる案件選択制を採用しています。そのため、成長したい分野や挑戦したい分野に専念することができます。
「不安があっても挑戦はしたい」「キャリアを本気で考えられる環境に身を置きたい」という方は、テクニケーションのカジュアル面談でお気軽にご相談ください。
契約形態の違いを理解して高還元SES企業で気持ちよく働こう

今回の記事では、SES契約についてさまざまな観点から解説をしました。SES契約はシステムエンジニアが活躍するために結ばなければならず、その概要を理解しておく必要があります。
そこで、下記でおさらいしてみましょう。
- SES契約では労働時間に対して報酬が支払われ、準委任契約では2つの契約タイプがある
- SES契約や準委任契約以外の契約形態
- SES契約の注意点・メリット・デメリット
- SES企業の選び方
SES契約は、指揮命令権の所在や実態などを確認したうえで行う必要があります。ぜひ本記事の内容を参考にして、スムーズにSES契約を進めましょう。
私たちテクニケーションでは、高還元を実現するために単価給与連動制を採用しています。これまで培ってきたスキルや経験に見合った報酬を得られるため、高いモチベーション維持につながっています。
また、企業間の単価をエンジニアに開示することにより、納得したうえで業務に臨むことが可能です。
その他、一人ひとりのキャリア形成が実現できるように、案件が自由に選択できる案件選択制も導入しています。
安心感を持って案件にチャレンジできる環境をお探しの方は、ぜひテクニケーションのカジュアル面談でお気軽にご相談ください。

















